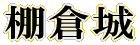 |
 |
| 別 名 |
亀ヶ城 |
| 所在地 |
福島県東白川郡棚倉町城跡 |
| 築城者 |
丹羽長重 |
| 築城年 |
寛永2年(1625) |
| 廃城年 |
慶応4年(1868) |
| 現 状 |
亀ヶ城公園 |
| 遺 構 |
郭・石垣・土塁・水堀 |
| 移築建造物 |
門 |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
国指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
棚倉城は寛永2年(1625)に丹羽長重が築いた近世城郭である。棚倉には南北朝時代から白河結城氏が地域支配の拠点とした赤館が存在し、戦国時代まで結城氏と佐竹氏が赤館を廻って激しい攻防戦を繰り広げた奥州の要衝でもあった。
慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで西軍寄りの行動を取った佐竹義宣は出羽久保田城へ転封となり、同じく西軍に身を投じて改易となっていた立花宗茂が大名に返り咲き赤館を居城としていたが、元和8年(1622)にやはり関ヶ原の戦いで西軍に味方して前田利長と戦い、改易された丹羽長重が5万石を与えられて赤館へ入城した。築城の名人でもあった長重は、旧式の城となった赤館に代わる居城として平城の棚倉城を築き新たな居城とした。
長重は寛永4年(1627)に白河小峰城へ移封となるが、奥州の名城である棚倉城、白河小峰城、そして二本松城がいずれも丹羽氏の手で今も見事な遺構を伝えていることはとても興味深い。丹羽氏に代わり譜代大名の内藤氏が棚倉城主となり、その後も松平氏、小笠原氏といった親藩と譜代大名が城主を歴任し、阿部正功が最後の城主のときに廃城となったが、棚倉藩は奥羽越列藩同盟に加盟していたため戊辰戦争では新政府軍の攻撃を受け、城主不在でわずかな守備兵しか残っていなかったために一日で落城した。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 棚倉城 |
|
追手門跡 |
|
長久寺 二ノ丸南門 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 二ノ丸 石垣 |
|
二ノ丸 石垣 |
|
本丸 水堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 本丸 水堀 |
|
本丸 水堀 |
|
本丸 犬走り |
|
 |
|
 |
|
 |
| 本丸 土橋 |
|
本丸 北桝形門 |
|
本丸 土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 本丸 土塁 |
|
本丸 土塁 |
|
本丸 土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 本丸 |
|
本丸 |
|
本丸 土塁と城址碑 |
|
 |
東白川郡の塙町から棚倉町にかけての城館探訪は好天に恵まれた。気温は低いものの寒さを感じるほどではなかったが、棚倉城へ移動した頃には日も陰り始め、冷たい北風が強く吹きつけて体感温度はかなり低く感じ、夕方に白河へ移動したときの気温は1度だった。
棚倉城もまたずっと訪ねてみたい城だった。丹羽長重は父長秀譲りの築城の名手である。当代の築城名人と言えば加藤清正と藤堂高虎が知られているが、長重は地味ながらも優れた城を数多く手がけている。築城だけでなく合戦も上手であり、慶長5年(1600)には関ヶ原の戦いの局地戦である浅井畷の戦いで、3千の兵力で前田利長が率いる2万5千の大軍を破っている。
その長重が築いた棚倉城は期待通りの名城だった。平穏な時代の城とは言っても、世の中はまだ戦国の気風を残していただけに、実戦を想定した縄張りを持っている。二ノ丸は原型を留めていないが、棚倉中学校に面した斜面には当時の石垣が顔を覗かせていた。地震の被害を受けたため一部が崩落しセメントで補強を受けているが、隅部の石垣は旧態と保っていて見事だった。民家の脇をすり抜けて遠慮がちに眺めなければならないのが残念ではある。
本丸は広々とした水堀が廻り、巨大な土塁が曲輪を取り囲んでいる。虎口は近世城郭らしい桝形虎口であり、城門があった時代はさぞかし壮観だったことが想像される。現存門は市街の北方にある長久寺に二ノ丸南門が移築されているが、小ぶりながら見事な門だった。奥州への裏街道の玄関口とも言える棚倉は、いかにも城下町らしい凛とした街並みが今も良く残っている。 |
 |
 |
JR水郡線「磐城棚倉」下車 徒歩10分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・城郭と城下町/小学館・棚倉城跡案内板 |
|
|
 |
2024/12/19 |
|
|
|
|