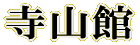 |
 |
| 別 名 |
蛇頭館・流館 |
| 所在地 |
福島県東白川郡棚倉町寺山 |
| 築城者 |
結城氏 |
| 築城年 |
戦国時代 |
| 廃城年 |
天正18年(1590) |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・土塁・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
寺山館は戦国時代に白河結城氏が築いたとされ、結城晴綱が深谷伊豆守を城代として守らせたと伝わる。この頃の結城氏は家中の内訌を経て弱体化の一途をたどっており、北進する佐竹氏は羽黒山館と東館を攻め落とし、永禄3年(1560)に佐竹義昭が寺山館を攻略した。
天正3年(1575)に佐竹義重は幾度かの敗戦を喫しながらも赤館を攻略するが、それまでは寺山館が佐竹氏にとっての最前線の拠点となった。今に残る巨大な連続堀切などは佐竹氏がこのときに増強したものだろう。赤館を攻略した佐竹氏は南郷衆を組織し、赤館を中心として寺山館、羽黒山館などを統治した。天正18年(1590)の小田原の役で佐竹義宣はいち早く豊臣秀吉に接近し、一躍54万石の太守となったが、秀吉から寺山館と羽黒山館を破却する命令が下り、どちらも破城が行われて廃城となった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 寺山館 |
|
登山道入口 |
|
西尾根 曲輪と土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 尾根道の土塁 |
|
桝形虎口 |
|
二の郭 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 |
|
主郭 土塁 |
|
主郭 桝形虎口 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 東尾根 堀切 |
|
東尾根 二重堀切 |
|
東尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 東尾根 堀切 |
|
東尾根 曲輪と土塁 |
|
東尾根 曲輪と土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 東尾根 曲輪 |
|
東尾根 曲輪と土塁 |
|
東尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 東尾根 曲輪と土塁 |
|
東尾根 堀切 |
|
寺山館からの眺望 |
|
 |
白河インターチェンジから東へ東へと進み、途中から南下して棚倉町を通過して塙町を目指した。この日の最大目標は羽黒山館だったが、文句のつけようがない素晴らしい山城の遺構を見ることができた。このあとは近在の城館を時間が許す限り立ち寄っていくことにしていたが、寺山館も特に予備知識もなく登った。
驚いたのは全国的にはほとんど無名に近い城館であるのに、至るところに道標が設置されていることだった。現地に到着していちばん困るのは登山道の入口を探すことであるが、寺山館についてはそれはまったく問題がなかった。山の麓に近づくと危険と記された看板があるのだが、ここがポイントで危険と示された道へ進まないと遠回りになってしまう。沢に架けられた心細い橋を渡ると再び寺山館への道標がある。
傾斜はそれほどでもなく特に疲れることもなく西尾根との分岐へと着いた。尾根の先端には土塁があり、傍らには小さな祠がある。おそらく物見の曲輪だったのだろう。道標に従ってさらに登ると中心部へ至る桝形が存在する。そこから三の郭と二の郭を通過して主郭へと至る。主郭には祠が並び土塁が残されている。東には立派な桝形虎口があり、そこからいよいよ東尾根へと進んでいった。
いきなり大きな堀切が尾根を断ち切り、曲輪の向こうにはさらに迫力を増した二重堀切が待ち受けていた。画像ではその迫力が半分も伝わらないが、なかなかお目にかかれないような堀切である。例えるなら長野県の仙当城のそれに近いほどの規模だった。分厚い土塁で囲まれた曲輪を越えていくと再び大きな堀切があり、曲輪を隔てて最後の堀切が現れるが、この堀切は林道建設のためにかなり破壊されていた。
その向こうには寺山館よりも標高のある山があるが、そこまでは城域には含まれていないようだった。林道で暫し休憩を取りながら、友人と寺山館の遺構について話し合ったが、お互い興奮が冷めやらず圧倒された気持ちだった。佐竹氏の拠点城郭である多気城に登ったことを思い出したが、その圧倒的な土木量は寺山館でも感じることができた。さすがに北関東から南奥州にかけてを制圧した名門だけのことはある。寺山館は国史跡レベルの遺構と規模を持つ山城だが、棚倉町の文化財指定すら受けていないのが不思議に思えた。これだけの名城があまり取り上げられていないことが残念に思う。地元でも力を入れて喧伝してもらいたいし、多くの人たちに知ってもらいたいと思いたくなるような山城だった。 |
 |
 |
JR水郡線「近津」下車 徒歩30分 |
 |
|
 |
福島県の中世城館跡/福島県教育委員会・寺山館跡案内板 |
|
|
 |
2024/12/19 |
|
|
|
|