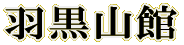 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
福島県東白川郡塙町塙 |
| 築城者 |
源義家 |
| 築城年 |
天喜2年(1054) |
| 廃城年 |
天正18年(1590) |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・石積・土塁・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
羽黒山館の伝承によれば天喜2年(1054)に源義家が築いたという。これはあくまでも伝承なので、実際には南北朝時代にその原型が築かれ、室町時代末期には佐竹氏の一族大塚氏が羽黒山館を拠点としていた。
永正2年(1505)には大塚氏が佐竹氏に背き白河結城氏に属した記録があり、天文10年(1541)に東館を攻略した佐竹氏が羽黒山館へ攻めかかった。その後は佐竹氏の南郷における有力支城となり、白河結城氏との攻防では寺山館とともに佐竹氏の最前線の拠点として、佐竹義重自ら赤館を攻略するために羽黒山館へ入った。
天正3年(1575)に赤館を攻略して南郷を制圧した義重は、赤館を中心として南郷衆を組織し、羽黒山館と寺山館は依然として重要な拠点としての役割を担った。天正18年(1590)に豊臣秀吉が北条氏を降して天下統一を果たすと、奥州仕置後の惣無事令によって羽黒山館と寺山館は破却された。慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで佐竹義宣は交流のあった石田三成に加担し、会津の上杉景勝と連携していた節があるが、そのときに佐竹軍は赤館まで進出しており、羽黒山館と寺山館も再び改修を受けた可能性は否めない。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 羽黒山館 |
|
東側斜面の曲輪 |
|
中心部の塁壁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 西側斜面の曲輪 |
|
西側斜面の曲輪 |
|
二の郭 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 堀切 |
|
主郭 櫓台 |
|
北尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 北尾根 曲輪 |
|
北尾根 堀切 |
|
北尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 北尾根 曲輪と土塁 |
|
北尾根 曲輪 |
|
北尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 北尾根 堀切 |
|
石積 |
|
羽黒山館からの眺望 |
|
 |
気の合う友人と奥州磐城の羽黒山館へ登る計画を立てた。奥州の玄関口となる白河から棚倉へと向かい、さらに南下して塙町へ到着したが、8時に出発して11時には登山を開始していたから順調な行程である。
羽黒山館は巨大であり、それほど整備の手が行き届いているとは言えないため探索には時間を要することが予測されたが、実際に出羽神社から先はまったくの未整備であり、堀切なども木に掴まりながら慎重に斜面を下る必要があった。
遺構は壮大かつ見事なもので、さすがに佐竹氏の拠点城郭だけのことはあった。佐竹氏の城郭を訪ねると規模が大きすぎて逆に実感が湧かないような堀切に出会うことがあるが、羽黒山館もまさにその通りで、この後に訪ねた寺山館と同様に堀切があまりにも巨大で画像にすると迫力がほとんど伝わらないのが残念である。目の当たりにするともう感嘆を通り越して呆れてしまうほどの規模だった。
日の当たらない曲輪はシダに覆われているが、藪ではないのでまずまず歩きやすい。堀切にはせめてロープぐらいは設置しておいてほしいと思うほどの傾斜であり、それは寺山館でも同様だった。最北端の堀切とそこから続く細尾根の途中までを見て羽黒山館での行動は終了となったが、塁壁の下には巨岩が転がっている箇所がいくつかあり、往時はある程度の石積が施されていた可能性がある。また東側の曲輪には用途不明の桝形があったりして面白味を感じた。
東北の城は巨大な山城であっても城とは呼ばず、楯や館と呼ばれることが普通だが、羽黒山館も城と呼ぶことが相応しいほどの面積と規模を持っている。この日は佐竹氏に関係のある城をいくつか回ることができたが、その気宇壮大な遺構を見るにつけ中世城館への憧憬がますます深まった一日となった。 |
 |
 |
JR水郡線「磐城塙」下車 徒歩30分 |
 |
|
 |
福島県の中世城館跡/福島県教育委員会・羽黒山館跡案内板 |
|
|
 |
2024/12/19 |
|
|
|
|