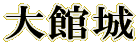 |
 |
| 別 名 |
岩城大館・好間館・飯野平城 |
| 所在地 |
福島県いわき市好間町下好間 |
| 築城者 |
岩城常隆 |
| 築城年 |
文明15年(1483) |
| 廃城年 |
慶長8年(1603) |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
いわき市指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
大館城は文明15年(1483)に岩城常隆が築いたと伝わる。岩城氏は桓武平氏の流れを汲む一族で、平安時代末期に平忠衡の次男隆衡が岩城郡を領有し岩城氏の祖となった。
当地の地頭は飯野八幡宮の宮司を勤める飯野氏であったが、鎌倉時代から南北朝時代にかけて岩城氏との確執を生じ、室町時代に入ると岩城氏は国人領主として発展を遂げていった。それまで岩城氏は白土城を居城としていたが、飯野氏の高月館を攻略した後に大館城を築いて居城とした。
戦国時代の岩城氏は相馬氏や田村氏との争いが激化し、常陸から北上して版図を拡大する佐竹氏にも押され、次第にその主導権を掌握されるようになり、岩城常隆は佐竹義重の三男貞隆を養子に迎えた。常隆が病没して家督を継いだ貞隆は豊臣秀吉に拝謁し、12万石の知行を安堵された。
慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで貞隆は兄の佐竹義宣が上杉景勝と連携したため会津征伐に参陣せず、戦後に佐竹氏は所領を半分に減らされて出羽久保田へ移封となったが、岩城氏は改易の憂き目を見ることとなった。貞隆はお家再興に奔走し大坂の陣に参戦して功を挙げ、信濃中村で1万石の大名として復帰した。
岩城氏に代わり10万石で領主となったのが鳥居元忠の子忠政である。忠政は大館城に代わる居城として慶長8年(1603)に磐城平城を築き、岩城氏代々の居城として君臨してきた大館城は廃城となった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 大館城 |
|
城址入口の道標 |
|
青雲院 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 空堀 |
|
空堀 |
|
曲輪 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 曲輪 |
|
二の郭 |
|
城址碑 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 虎口 |
|
主郭 |
|
主郭 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 |
|
礎石 |
|
西尾根 曲輪 |
|
 |
福島県はこれまでに何度か訪れているが、浜通りの城は相馬中村城の他は数えるほどしか訪ねていない。行ってみたい気持ちはあったが、東日本大震災があって結局はずっと行けないままでいた。
復興も進み、常磐線も全線で復旧したこともあり、ようやく機が熟した感があったので、上野駅から特急ひたちに乗車して終点のいわき駅を目指した。行きの車内は混んでいたが、水戸を過ぎると空席ばかりとなった。途中の日立や高萩を通過するときには太平洋が車窓に広がり、なかなか風光明媚な旅となった。
いわき駅で降りれば目の前に磐城平城があるので、最初はそちらに向かい、高月館を経由して大館城を訪ねた。この頃には陽射しも強まり、真夏のような気温となった。さすがに5月中旬を過ぎると山城は蜘蛛の巣が多く、小さな虫も飛び交ってストレスが溜まる。城址入口から途中までは住宅街であり特に苦労もなかったが、中腹から大館城の中心部までは舗装された道を歩けるものの、濃い緑に覆われた山道のようだった。
途中には曲輪がいくつかあり、湯殿神社への参道は堀底道となっている。草木が生い茂っているのであまり深くは探索せず、主郭を中心に見ただけだが、長くこの地を支配した岩城氏の居城にしては物足りない印象を受ける。巨大な土塁もなければ、深い堀切も見られず肩透かしを喰らった感じだが、実際の大館城の城域は周辺の丘陵一帯にまで広がっていたらしく、付近の寺院や神社も丘の上に構えられていて、ひとつひとつが砦のような雰囲気を持っていた。
暑さもあっていわき市の城館探訪はここで切り上げたが、天気も上々で楽しい探訪となった。いわき駅に戻って1時間ほど時間を費やして帰路の特急に乗車したが、水戸まではやはり空席ばかりで勿来を過ぎたあたりから勝田まではほとんど寝ていた。 |
 |
 |
JR常磐線「いわき」下車 徒歩40分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・福島県の中世城館跡/福島県教育委員会 |
|
|
 |
2025/05/21 |
|
|
|
|