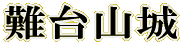 |
 |
| 別 名 |
男体城 |
| 所在地 |
茨城県笠間市上郷 |
| 築城者 |
小田藤綱 |
| 築城年 |
元中4年/嘉慶元年(1387) |
| 廃城年 |
元中5年/嘉慶2年(1388) |
| 現 状 |
吾国・愛宕県立自然公園 |
| 遺 構 |
郭・土塁・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
茨城県指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
難台山城は南北朝の争乱期である嘉慶元年(1387)に小田五郎藤綱が築いた山城である。鎌倉公方足利氏満に反抗して敗死した小山義政の遺児若犬丸は常陸へと逃れ、南朝の残党たち若犬丸がを擁立し難台山城で挙兵した。
対する北朝は上杉朝宗を総大将として攻めかかるが、難台山城は容易に落ちることなく寡兵ながらも大軍を相手に持ち応えた。朝宗は付け城として舘岸城に陣取り持久戦に持ち込み、攻城軍に加わった佐竹氏の軍勢が糧食を絶つことに成功し、難台山城は落城して藤綱は自刃した。若犬丸は落城前に逃亡したが、その行方については諸説あり、応永4年(1397)に会津で自刃したとされている。
小田氏の乱が鎮圧された後の難台山城は、峻険な山城のため他勢力に使われることなく廃城となり、その後も再び取り立てられることはなかったらしい。逆に言えばそのおかげで今も南北朝時代の山城の姿を色濃く残している。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 難台山城 |
|
団子石 |
|
登山道 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 獅子ヶ鼻 |
|
南尾根 堀切 |
|
石積 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 南尾根 曲輪 |
|
屏風岩 |
|
主郭 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 東尾根 堀切 |
|
東尾根 堀切 |
|
難台山城からの眺望 |
|
 |
南朝の勢力が小山若犬丸を迎えて立て籠もった難台山城は、遺構の優劣は別として一度は訪れてみたい山城だった。南北朝時代の山城は戦国時代のような技術はまだ発達しておらず、天険の要害を利用したものが多いが、難台山城もその例に洩れず手の込んだ遺構は見られない。しかしその時代背景にはたまらないほどの魅力を感じる山城であるし、遺構の乏しさはこの城が短命に終わったことを如実に示している。
岩間駅周辺にはほとんど店がなかった。今でも少し地方へ行くとコンビニすらない街がたくさんあるが、地元の人たちはそれを当たり前のものとして普通に暮らしている。そんな光景を見ると都市近郊のコンビニの異常な出店数については考えさせられてしまう。しかし今回は長丁場となるので何とか店を探して弁当を買い込んだ。
駅から林道まではほとんど一直線なので迷うこともなかった。難台林道と団子坂林道の分岐では舗装された団子坂峠への道を選んだ。岩間駅から峠まではおよそ1時間半かかったが、緩やかな坂なので疲れは感じない。峠から難台山城までの道のりは長く、急勾配や岩場伝いの場所があるので疲労する。おまけに前日までの雨続きでぬかるみがひどく、悪戦苦闘しながらも峠から45分で山頂へ着いた。山頂からの眺望は今ひとつだったが、暑さも寒さも感じないちょうど良い気候だったので、弁当を広げてしばらくのんびりしていた。
山頂へ至る途中でいくつかの曲輪らしい地形が見られ、荒々しい屏風岩の付近に堀切が残っている。山頂の主郭はこれといった造作は見られず、東と西に伸びる尾根にはささやかな堀切がある。
南西に延びる尾根にも遺構があるのだが、ぬかるんだ急斜面を下る気にはなれず、そのために案内板や小田五郎の碑は見ていない。尾根伝いに歩けば泉城と愛宕山城へ行くことができるが、かなり距離を歩いたこともあり、無理はせずに岩間駅へ戻ることにした。 |
 |
 |
JR水戸線「岩瀬」下車 徒歩2時間30分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社 |
|
|
 |
2018/03/24 |
|
|
|
|