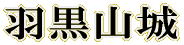 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
茨城県桜川市西小塙 |
| 築城者 |
春日顕国 |
| 築城年 |
延元4年/暦応2年(1339) |
| 廃城年 |
− |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・石積・土塁・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
南北朝時代に南朝方として戦った春日顕国が築いたと伝わる。茨城県は戦前の皇国史観の影響が色濃く残り、そのおかげであまり知られていないような山城でも標柱が設置されていることが多い。羽黒山城は同じ峰続きにある棟峰城入口の標柱はあったが、羽黒山城についての標柱や案内板はなかったと記憶している。
南朝の拠点として名前だけが残り、今もなお場所がわかっていない中郡城がこの城なのかもしれないが、それぐらい規模も遺構も見事な山城である。しかし今に残る遺構から南北朝時代の城とは思えず、戦国時代の改修が加わっていることは確かであり、笠間氏の一族が羽黒山城に在城していたというが、あくまでも軍記による出典であり確かなことはわからない。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 羽黒山城 |
|
登山道入口 |
|
登山道 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 四の郭 土塁 |
|
三の郭 土塁 |
|
二の郭 土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 虎口 |
|
主郭 虎口 |
|
主郭 石積 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 土塁 |
|
主郭 |
|
五の郭 横堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 五の郭 横堀 |
|
六の郭 堀切 |
|
羽黒山城からの眺望 |
|
 |
この年の2月は記録的な寒波が日本列島を襲った。関東地方もちょっと記憶にないほどの厳しい寒さに見舞われた。例年なら山城探訪が楽しい時期だが、温暖な千葉県でも手が凍えたほどで冷え込む山城へ行く気持ちは起きなかった。
3月になると寒さも和らいで春の足音が聞こえてきた。久しぶりに青春18きっぷを購入して関東近郊の山城を廻ることにした。その関東地方もほとんど行き尽くした感があり選択にはかなり迷ったが、友人が羽黒山城は良かったと言っていたことを思い出した。桜川市は遠く感じていたが、宇都宮線で小山まで出て水戸線に乗り換えるとそれほど遠い感じはしなかった。
羽黒駅からでも羽黒山はよく見える。西麓から登山道を登るが久しぶりに味わう急な山道だった。ロープに掴まりつつ登り切ると四の郭の堀切へ着いた。手入れがされているわけでもなく城跡は藪に覆われていたが、主郭とその周辺はすっきりとしていた。土塁の規模は甲斐の要害山城のそれを彷彿とさせるほどで、石積による補強が施されている。
南北朝時代に南朝の軍勢がこの城を築いたというが、洗練された遺構は戦国時代まで使用されたことを物語っている。主郭に残る石積はその証拠となるだろう。尾根続きにある棟峰城へ訪れたあとは再び同じ道をたどって下山した。久しぶりの山城で疲れはしたが爽快だった。素晴らしい遺構と美しい眺望に酔いしれて上機嫌で山を下りた。 |
 |
 |
JR水戸線「羽黒」下車 徒歩50分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社 |
|
|
 |
2018/03/02 |
|
|
|
|