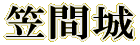 |
 |
| 別 名 |
桂城 |
| 所在地 |
茨城県笠間市笠間 |
| 築城者 |
笠間時朝 |
| 築城年 |
承久元年(1219) |
| 廃城年 |
明治4年(1871) |
| 現 状 |
佐志能神社・山林 |
| 遺 構 |
郭・石垣・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
櫓 |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
笠間市指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
笠間城は承久元年(1219)に笠間時朝が築いた山城である。鎌倉時代は武装した僧兵が全盛を極めた時代であり、笠間城も僧兵たちの対立によって生まれた城と言える。当初は佐白山に麓城が築かれ正福寺の僧兵たちは宇都宮氏の支援を受けて敵対する徳蔵寺の勢力を討滅したが、正福寺は味方として派遣された笠間時朝に反旗を翻したため、時朝は正福寺を討ち果たし佐白山に山城を築いた。
その後は長きに亘って笠間氏の居城となったが、戦国時代末期に笠間氏は主家の宇都宮氏との折り合いを欠き、笠間城を攻め落とされて滅んだ。豊臣大名となった宇都宮氏も改易されたため蒲生秀行の家臣蒲生郷成が入城し、近世城郭としての改修が施されている。
江戸時代には笠間藩の居城として浅野氏を除いては譜代大名が歴代藩主に名を連ねている。牧野氏の8万石を最高とする小藩でありその維持も苦労が多かったと思われるが、実際に政務の中心となったのは山麓の下屋敷と呼ばれる一帯だった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 笠間城 |
|
大黒石 |
|
千人溜り跡 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 大手門跡 |
|
大手 空堀 |
|
大手 石垣 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 大手 石段 |
|
大手 石段 |
|
八幡台櫓跡 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 本丸 |
|
本丸 土塁 |
|
石碑 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 天守曲輪 石段 |
|
天守曲輪 石垣 |
|
天守曲輪 石段と石垣 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 天守台 石垣 |
|
佐志能神社 |
|
天守の瓦 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 天守曲輪跡 |
|
笠間城からの眺望 |
|
真浄寺 移築された八幡台櫓 |
|
 |
学生時代の旧友と久しぶりに再会した。3人で会うのは20年ぶりぐらいだったと思う。せっかくの再会だから少し遠くへ出かけることになり5月中旬の晴れた日に笠間城を訪れた。陽射しはあったが千人溜り跡の駐車場で車から降りたときはひんやりとしていた。山を覆う森に冷やされた空気がとても心地よかったことを覚えている。とても自然の豊かな城跡であり城の遺構もよく残っている。
石段を登る途中にある苔むした石垣が美しかったし天守曲輪の石垣も立派だった。この見事な石垣は東日本大震災で崩壊したので崩れる前の姿を見ておいて良かったと思う。石垣の修復はとても時間がかかる作業だし重機が入る以上は遺構の破壊を伴う。今の笠間城がどうなっているのかはわからないが当時と変わらない姿に戻ってくれていることを願う。
佐志能神社を支える土台は笠間城の石垣と屋根瓦の旧材が使われている。城の瓦がこのように再利用をされているのは珍しい。好天と緑に包まれた山中を散策したあとは麓の真浄寺に移築された八幡台櫓へ立ち寄った。ほとんどそのまま移築されたようで櫓の姿そのものだった。笠間城は美しい城だと思うし石垣の修復が終わったのであればもう一度訪れてみたい。 |
 |
 |
JR常磐線・水戸線「友部」下車 市内周遊バスで「日動美術館」下車 徒歩20分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・城郭探検倶楽部/新人物往来社 |
|
|
 |
2008/05/17 |
|
|
|
|