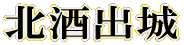 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
茨城県那珂市北酒出 |
| 築城者 |
佐竹助義 |
| 築城年 |
鎌倉時代 |
| 廃城年 |
− |
| 現 状 |
宅地・農地 |
| 遺 構 |
土塁 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
北酒出城は佐竹秀義の子八郎助義が、文治5年(1189)の奥州征伐で軍功を挙げ、北酒出に領地を与えられて北酒出氏を名乗ったときに築いたとされる。同じ台地続きには兄の南酒出義茂が築いた南酒出城が存在している。
助義は承久3年(1221)に起きた承久の乱で活躍し、その恩賞として与えられた美濃へ赴任した。そのため北酒出城での在城期間は短く、ほとんど未完成のまま廃城となったらしく、その後も再利用されることなく廃城になったようである。 |
 |
|
|
 |
南酒出城は自分の想像を遥かに超える見事な城郭だった。佐竹氏の居城としては長くその本拠地となった太田城が、ほとんど地表面に痕跡を残しておらず、水戸城も佐竹氏の居城となった期間が短い上に、江戸時代を通じて徳川御三家の水戸徳川家の居城となったため、佐竹氏時代の痕跡というのはわからなくなっている。南酒出城は築城から廃城に至るまで佐竹氏の支配下に置かれていたため、その築城様式を後世へ伝えてくれる貴重な文化遺産となっている。
豪快な南酒出城の遺構を味わったあとに訪ねたこともあり、北酒出城はかなり分が悪かった。東の田園地帯から遠目に眺める北酒出城は、台地先端を利用した城跡らしい地形に見えるが、完成の域まで達していなかったために遺構はほとんど残らず、主郭跡に塚が残されているだけだった。北酒出城の南にある駒形神社は、南酒出義茂が宇治川合戦で失った愛馬の慰霊のために創建したとされている。 |
 |
 |
JR水郡線「南酒出」下車 徒歩25分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・茨城の古城/筑波書林 |
|
|
 |
2019/04/01 |
|
|
|
|