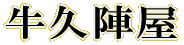 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
茨城県牛久市城中町 |
| 築城者 |
山口重政 |
| 築城年 |
寛永5年(1628) |
| 廃城年 |
明治4年(1871) |
| 現 状 |
農地 |
| 遺 構 |
門・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
牛久陣屋は寛永5年(1628)に山口重政が1万石で構えた陣屋である。山口氏の本姓は多々良氏で周防の名族大内氏に繋がり、重政は尾張寺部城の山口重勝の養子となり織田信雄に仕えた。
天正18年(1590)の小田原の役における論功行賞で、信雄が豊臣秀吉の怒りを買って改易されると、重政は徳川秀忠に仕えて1万石を与えられた。慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで重政は秀忠に従軍し、信濃上田城攻めの功によって牛久城主となるが、慶長18年(1613)に大久保忠隣の失脚に連座して改易された。
慶長20年(1615)に大坂夏の陣で戦功を挙げ、牛久藩主に返り咲き牛久城の一画に陣屋を構え、1万石で立藩した牛久藩は山口氏が代々の藩主を勤め明治4年(1871)まで存続した。 |
 |
|
|
 |
牛久城には2度訪れており牛久陣屋にも同じ数だけ足を運んでいる。牛久城は思っていたよりもずっと広大で見事な遺構が楽しめる城だった。そこから外郭をたどり牛久城の西側へ続く台地に構えられた牛久陣屋を訪れたが、跡地は一面の畑となって何もないというのが印象で河童の碑だけを撮影して帰路についた。
2度目の訪問時、友人のひとりが土塁がある場所を教えてくれたが、真一文字に続くその姿は見れば見るほど立派なもので、牛久城時代の遺構をそのまま流用したものと思う。木陰から眺める牛久沼の夕陽がとても美しい日だった。 |
 |
 |
JR常磐線「牛久」下車 市内循環バスで「河童の碑入口」下車 徒歩1分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社 |
|
|
 |
2008/12/07・2015/12/19 |
|
|
|
|