 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
茨城県那珂市瓜連 |
| 築城者 |
建武3年(1336) |
| 築城年 |
楠木正家 |
| 廃城年 |
− |
| 現 状 |
常福寺 |
| 遺 構 |
郭・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
茨城県指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
瓜連城は建武3年(1336)に南朝の雄である楠木正成に派遣された楠木左近蔵人正家が築いたという。正家は正成の一族と思われるが、その血縁関係ははっきりとしていない。正家は南朝の主力となった北畠顕家が不在の間、広橋経泰、小田治久らを糾合し、常陸における北朝勢力の佐竹氏の討伐を目論んだ。
瓜連城の戦いでは佐竹軍の後藤七郎基明が討死し、増援が見込めない佐竹軍は金砂山城に立て籠もった。やがて北朝の増援部隊が到着し、佐竹軍は攻勢に転じたが、瓜連城の守りは堅く再び山岳地帯へ撤退した。
佐竹軍は武生城から佐竹義篤が出撃し、一族の馬淵義景も救援に駆けつけたため南朝方の城砦は各個撃破され、瓜連城も窮地に立たされることになり、楠木軍の主力は撤退を開始し瓜連城は落城した。
形勢不利となった南朝方は北畠親房が常陸へ上陸し、分断された勢力の結集を試みたが、北朝方は高師冬を差し向けて対抗した。しかし下総から転戦した師冬の軍勢は連戦で疲れ果てており、暦応3年(1340)に宇都宮から瓜連城へ入城し兵力の回復を図った。この翌年に南朝方は勢いを盛り返し、大和から興良親王が小田城へ迎えられると、師冬は瓜連城から出撃して小田城を包囲した。この時を最後に瓜連城は歴史に登場してこないことから、南北朝時代のごく限られた期間のみ存続していたと考えられている。 |
 |
 |
|
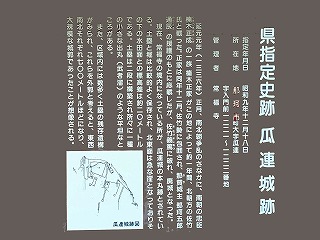 |
|
 |
| 瓜連城 |
|
案内板 |
|
常福寺 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 土塁と空堀 |
|
土塁 |
|
空堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 曲輪 |
|
土塁 |
|
土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 虎口 |
|
土塁 |
|
土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 空堀 |
|
横堀 |
|
横堀 |
|
 |
風薫る5月の城廻りは爽やかな気持ちにさせてくれる。ちょうど1年前にも茨城県の城館探訪をしていたが、この日も連休中の混雑を避けるために茨城県の城を訪ねた。
これまで訪れたことがなかった常陸大宮以北の城を訪ねることで、前日から気持ちが前のめりになっており、当日もそれは変わらなかった。最初に向かったのは瓜連城であるが、事前の知識は多少の遺構があるといった程度で、かなり軽い気分で訪れた。主郭と思われる場所は常福寺の境内となっているが、墓地の手前にかなり大きな空堀と土塁が残されている。保育園の奥には杉林となった曲輪が残り、ここにもしっかりとした土塁が残っていた。北へ向けて虎口が開口しており、そこから下りると見事な切岸とそれに付帯する横堀が残っていた。
源太郎稲荷神社が祀られている土塁はまるで近世城郭のような規模を誇っている。これだけ見ると瓜連城が南北朝時代のごく限られた期間だけ存続したというのが疑わしくなってくる。戦国時代になっても佐竹氏によって維持されていたのではないかと思うのだが、これについては記録が残っていないため通説に従うしかないようだった。 |
 |
 |
JR水郡線「瓜連」下車 徒歩15分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・茨城の古城/筑波書林・瓜連城跡案内板 |
|
|
 |
2025/05/01 |
|
|
|
|