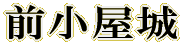 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
茨城県常陸大宮市泉 |
| 築城者 |
平沢通行 |
| 築城年 |
鎌倉時代 |
| 廃城年 |
慶長5年(1600) |
| 現 状 |
種生院・山林 |
| 遺 構 |
郭・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
| |
 |
| |
 |
前小屋城は那珂氏の一族とされる平沢丹後守通行が築いたという。年代までは特定されていないが、建武3年(1336)に瓜連城が落城すると、南朝に味方していた那珂通辰は北朝の佐竹貞義の反撃を受けて自刃しており、通行は那珂氏が滅んだ後に佐竹氏の家臣となっているので、鎌倉時代には築城されていたと推定される。
戦国時代には佐竹氏の一族小場義忠の弟義広が前小屋城を本格的な城郭として改修し、自ら城主となって前小屋氏を名乗った。慶長5年(1600)に佐竹氏領内の所領再編で小場義宗は小田城へ配置されることとなり、前小屋氏も従ったため前小屋城は廃城となった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 前小屋城 |
|
案内板 |
|
三の郭 土塁と空堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 二の郭 |
|
二の郭 二重土塁 |
|
二の郭 土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 二の郭 空堀 |
|
二の郭 空堀 |
|
主郭 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 土塁 |
|
主郭 土塁 |
|
主郭 虎口 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 空堀 |
|
主郭 空堀 |
|
仲屋敷 虎口 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 仲屋敷 土塁 |
|
仲屋敷 空堀 |
|
仲屋敷 空堀 |
|
 |
好天に恵まれた5月に常陸の城館探訪に出かけた。今回はそのほとんどが佐竹氏に関連した城郭である。佐竹氏の城郭はどれも土塁や空堀の規模が気宇壮大で圧倒されるが、今回もそのような城郭が多かった。
前小屋城はとても良いと聞いていたので、途中で立ち寄ることにしたが、噂に違わぬというか、想像を大きく上回る巨大な城だった。城址に建つ種生院の道案内に従って路地を進んでいくと、農地の脇に巨大な土塁が残っている。三の郭と四の郭は大部分が畑となっているため立ち入ることは控え、主郭である種生院へ向かったが、その途中に二の郭の二重土塁と深い空堀に目を奪われた。道の西半分しか残っていないが、それでも十分すぎる遺構である。
主郭には三蔵法師が立ち寄ったという歴史を持つ種生院の観音堂が建っている。主郭を囲む土塁は大部分がよく残り、特に南西隅の土塁は高さもあって迫力を感じさせてくれた。西側に虎口があり、空堀を挟んで仲屋敷と呼ばれる曲輪がある。ここは少々藪化しており、立派な土塁も撮影すると今ひとつ規模の大きさが伝えきれない。さらに西にも城域が展開していそうだが、とりあえずはここまでとした。
久米城や山入城といった有名な城の陰に隠れがちで、前小屋城の知名度は必ずしも高くないが、遺構の素晴らしさは他の佐竹氏系の城郭にまったく劣らないどころか、自分の中では上位に位置づけされる城となった。 |
 |
 |
JR水郡線「常陸大宮」下車 茨城交通バス「水戸駅」行で「泉入口」下車 徒歩15分 |
 |
|
 |
茨城の古城/筑波書林・前小屋城跡案内板 |
|
|
 |
2025/05/01 |
|
|
|
|