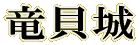 |
 |
| 別 名 |
久米西ノ城 |
| 所在地 |
茨城県常陸太田市久米町 |
| 築城者 |
小野崎通種 |
| 築城年 |
室町時代 |
| 廃城年 |
慶長7年(1602) |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・土塁・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
竜貝城は久米城の北側を守るために築かれた城である。久米城は鎌倉時代に大掾氏に築かれたという伝承があるが、本格的な山城としての体裁が整えられたのは室町時代に小野崎氏が城主となったときのことであろう。
あるいは小野崎氏の時代に本城が築かれ、後に佐竹氏の宗家と山入氏が激しく争った時代にそれぞれの出城が増築されたのかもしれない。本城と竜貝城は似たような造りなので、築城年代にそれほどの差異はないと思われる。戦国時代には佐竹北家の居城となり、慶長7年(1602)に佐竹義宣が出羽久保田へ移封されたときに佐竹義兼もそれに従い、久米城と竜貝城を含む出城群は廃城となった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 竜貝城 |
|
腰曲輪 |
|
堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 |
|
物見台 |
|
堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 二の郭 土塁 |
|
二の郭 土塁 |
|
堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 三の郭 土塁 |
|
三の郭 土塁 |
|
三の郭 土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 腰曲輪 |
|
堀切 |
|
竜貝城からの眺望 |
|
 |
竜貝城は久米城の別曲輪であるが、現地の図面を参照しても主郭や二の郭といった表記があり、谷を挟んで独立したような立地なので久米城とは別々に扱うこととした。
曲輪の配置は久米城と大差なく、東西に3つの曲輪が並び、その南側に腰曲輪がひな壇のように配置されている。主郭にはテレビの中継所が建設されているが、その背後には物見台と呼ばれる土壇があり、ここからの眺めは美しかった。久米城はほとんど眺望が遮られていただけに竜貝城から見下ろす風景を眺めつつ、ここまでの長旅の疲れを癒すことができた。
出城とはいってもそれぞれ独立した曲輪があり、それらを堀切が断ち切っている。この堀切たちも久米城ほどの規模はないものの、しっかりと尾根を断ち切る立派な堀切だった。久米城にはあまり見られなかった土塁が曲輪に盛られており、このあたりは多少の年代差を感じる。主郭から北へ派生する尾根の先には北の出城と呼ばれる曲輪があるが、図面で見る限り規模はそれほどではないので割愛し、南の出城を目指すことにした。 |
 |
 |
JR水郡線「常陸太田」下車 茨城交通バス「上宮田代」行で「久米十文字」下車 徒歩40分 |
 |
|
 |
茨城の古城/筑波書林・関東の名城を歩く/吉川弘文館・久米城跡案内板 |
|
|
 |
2025/05/01 |
|
|
|
|