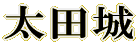 |
 |
| 別 名 |
舞鶴城・佐竹城・北城 |
| 所在地 |
茨城県常陸太田市中城町 |
| 築城者 |
太田通延 |
| 築城年 |
天仁2年(1109) |
| 廃城年 |
慶長7年(1602) |
| 現 状 |
太田小学校 |
| 遺 構 |
土塁 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
太田城は天仁2年(1109)頃に藤原秀郷の後裔太田大夫通延によって築かれたとされる。その後は佐竹四郎隆義が太田通盛を従属させ、佐竹氏の惣領家を継承して太田城主となった。
治承4年(1180)に源頼朝が平氏追討のために挙兵したが、同じ源氏の佐竹氏は敵対したため頼朝に軍勢を差し向けられた。佐竹一族は要害性に乏しい太田城から金砂山城へ移って籠城したが敗れた。隆義と秀義父子は許されたが所領を没収され、その所領は八田知家に与えられたが、後に隆義は常陸へ戻り再び太田城へと入った。
応永14年(1407)に佐竹義盛が世継ぎのないまま没したため、重臣たちは関東管領上杉憲定の次男龍保丸を養子に迎え、龍保丸は佐竹義人と名乗り13代目当主となった。源氏の正当な血筋を受け継ぐ佐竹氏が他家から養子を迎えることに不満を持った同族の山入与義らは、義人の入国を阻止すべく与党を募り反抗し、これが佐竹氏宗家と山入氏とのおよそ百年に亘る抗争の端緒となった。
延徳2年(1490)に山入義藤は太田城を急襲し、佐竹義舜を孫根城へ撤退させ太田城を占拠した。義藤は14年に亘り太田城を占拠したが、明応元年(1492)に没した。これを機会に佐竹氏と山入氏は和睦を模索したが、山入氏義は太田城を明け渡さず、金砂山城に撤退した義舜は小野崎氏らの支援を受けて太田城を奪還した。
戦国時代には板東太郎と畏怖された佐竹義重が当主となり、名門小田氏を圧迫し、さらには奥州へ出兵して精力的に活動し、周辺諸国からは鬼義重と恐れられた。義重の嫡男義宣が家督を相続すると、織田信長と誼を通じ、さらには豊臣秀吉とも友好関係を築くなど、巧みな外交戦略を行い、天正18年(1590)の小田原の役に参陣し常陸一国54万石の太守となった。
このとき義宣は領内の国人衆を酒宴と称して呼び集め殺害し、その所領を強引に奪い取り、江戸重通を武力行使で退去させて水戸城を手中に収め自らの居城とした。太田城は父義重の隠居城として存続したが、慶長7年(1602)に義宣は出羽久保田へ国替えを命じられ、太田城は廃城となった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 太田城 |
|
本丸 城址碑 |
|
三ノ丸跡 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 西側の城壁 |
|
西側の城壁 |
|
駒柵砦 |
|
 |
長く佐竹氏の居城として君臨した太田城だが、現状は学校や宅地が建ち並び遺構はほとんどが失われてしまった。川に面した舌状台地という佐竹氏が好んだ立地の城だが、高台であることが災いして住宅開発によって跡形もなくなっている。
太田小学校が本丸と三ノ丸に跨り、校門を入ると太田城の別名である舞鶴城と刻まれた石碑が建立されている。太田第一高校が北曲輪で専売公社跡地が三ノ丸に該当し、二ノ丸には太田進徳幼稚園や若宮神社が建ち並ぶ。
出城の役割を備えた帰願寺が駒柵砦の跡で多少ながらも城砦らしい雰囲気が感じられた。西側から太田小学校の校地を見上げると太田城の往時を偲ばせるような城壁が立ちはだかる。遺構が皆無に等しい太田城の中でここだけが当時の雰囲気を知ることができる場所だと思う。
残念ながら佐竹氏の栄耀栄華を見守り続けた太田城の現況は寂しい限りであるが、それを承知で訪ねてみたい城だっただけに、実際に訪問できたことはとても嬉しく思えた。惜しむらくは失われた城であっても曲輪跡に案内板や標柱ぐらいは設置できるはずなので、郷土の歴史を後世へ伝える意味でも常陸太田市には頑張ってもらいたいと思った。 |
 |
 |
JR水郡線「常陸太田」下車 徒歩30分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・茨城の古城/筑波書林 |
|
|
 |
2025/05/01 |
|
|
|
|