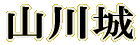 |
 |
| 別 名 |
山川館・地蔵屋敷 |
| 所在地 |
茨城県結城市上山川 |
| 築城者 |
山川重光 |
| 築城年 |
建仁年間(1201〜04) |
| 廃城年 |
永禄8年(1565) |
| 現 状 |
東持寺 |
| 遺 構 |
郭・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
結城市指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
山川城は建仁年間(1201〜04)に結城朝光の四男山川重光が築いた平城であり、その後は戦国時代まで山川氏の居城となった。山川氏は本家の結城氏に仕え結城四天王に名を連ね、永享12年(1440)の結城合戦でも結城城の籠城に参加した。
天文3年(1534)に多賀谷氏が常陸の小田氏と結び結城氏からの独立を図ると、山川尾張守は多賀谷氏の討伐に向かったが、多賀谷家重の抗戦の前に撤退を余儀なくされた。天文6年(1537)に多賀谷氏と小田氏の連合軍が山川氏の領内へ侵攻を開始すると、結城政勝は古河公方と祇園城の小山氏と連携し夜襲を敢行し、多賀谷氏の居城である下妻城へ進撃したが両者は和睦した。
その後も山川氏は結城氏とともに小田氏との抗争に明け暮れたが、上杉謙信が関東へ出馬した永禄3年(1560)に山川氏重は謙信の幕下へ参陣した。家の保全のために山川氏重は北条氏と上杉氏との間で揺れ動き、永禄8年(1565)には山川綾戸城を築いて新たな居城とした。その後の山川城がどのように利用されたかは不明だが、慶長6年(1601)に結城秀康が関ヶ原の戦いの論功行賞で越前北庄城へ移ると山川氏もともに越前へと移った。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 東持寺 |
|
土塁と空堀 |
|
土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 土塁 |
|
土塁 |
|
土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 土塁と空堀 |
|
土塁と空堀 |
|
土塁 |
|
 |
山川氏が支配した山川郷は近くて遠い場所だった。公共交通機関で訪れることはかなり大変であり、ずっと訪ねることができないでいたが、友人と茨城県内の城館探訪ができたおかげで訪れる機会がやってきた。
山川城は東持寺の境内がそのまま当てはまる典型的な方形居館であり、足利氏館跡の鑁阿寺や山梨市の連方屋敷のような雰囲気を漂わせている。土塁と堀が境内の周囲を取り囲む様は壮観であり、板東武者の居館に相応しい風格を兼ね備えている。土塁と空堀の規模は大きく、戦国時代まで改修を加えられながら存続してきたことがよくわかる遺構だった。往時はもっと堀は深く土塁は高かったろうし、その角度もさらに鋭いものだったはずである。長年の風雪で崩れかけていることを考慮しても、武士の館跡が持つ荒々しい迫力をよく伝えていると思う。この日はいくつかの方形居館を訪ね歩いたが、その中でも山川城の遺構は特筆すべきものだった。 |
 |
 |
JR水戸線「結城」下車 結城市巡回バス「芝崎」下車 徒歩15分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・茨城県の中世城館/茨城県教育委員会 |
|
|
 |
2025/10/09 |
|
|
|
|