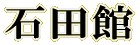 |
 |
| 別 名 |
平国香館・石田営所 |
| 所在地 |
茨城県筑西市東石田 |
| 築城者 |
平国香 |
| 築城年 |
昌泰元年(898) |
| 廃城年 |
承平5年(935) |
| 現 状 |
農地 |
| 遺 構 |
− |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
後に関東を席捲した板東平氏の礎を築いた平国香が構えた石田館の推定地である。国香は平高望の長男として生まれ、平将門の叔父にあたる。昌泰元年(898)に上総介に任じられた国香は板東へ下向し、筑波山の西麓にある真壁郡東石田に居館を構え、源護の娘を娶り常陸大掾職を譲り受け、関東における坂東平氏の勢力を拡大させた。
承平5年(935)に甥の将門と国香は野本の戦いで交戦し、石田館に火をかけられて戦死した。これを受けて子の平貞盛は板東へ戻り将門との和睦を模索したが、一族に説得されて将門と対決姿勢を取り、これが後の天慶の乱の発端となる。 |
 |
|
|
 |
五霞町から始まった茨城県内の城館探訪は古河市、結城市を経て八千代町から筑波山へと近づいた。いつ見ても美しい山容にはうっとりとさせられる。かつての真壁郡は市町村合併によって筑西市となった。筑波山の西という意味合いなのだろうが、平仮名のつくば市やつくばみらい市などといった曖昧でどこの街なのかわからない呼称よりずっと良いと思う。
東石田の集落は細く折れ曲がった路地ばかりで移動には難儀である。国香の館は台地の北にある鹿島神社付近という説が濃厚だが、何せ遠い昔の平安時代の館ということもあり、はっきりとした場所は確認しようがない。石田館は平将門に攻められたときに炎上したというから、発掘で焼土層が検出されれば手がかりになるのだろうが、そこまでする必要もないと思う。
鹿島神社には立ち寄らず国香の墓と伝わる場所を訪ねてみた。墓と伝えられる場所は2箇所あり、いずれも案内板が設置されている。ひとつは完全に民家の奥なので立ち入るのに躊躇したが、家人の姿は見えるものの声をかけても返答がないので、見学は黙認されているのだろうと思い、敷地内の奥まで入り撮影した。
もうひとつの場所はさらに東の畑の中にある。樹木の傍らにぽつんと残る自然石が墓標という。ここもまた筑波山の麓に広がる平野を見下ろせる景勝地であり、国香の館があってもおかしくない雰囲気に思えた。土塁らしい遺構もあるが、平安時代に滅んだ館の遺構とは思えない。どちらにしても平安の昔の息吹きを感じられるだけで十分だった。 |
 |
 |
つくばエクスプレス「つくば」下車 関東鉄道バス「筑波山口」行で終点下車 徒歩50分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・平国香の墓案内板 |
|
|
 |
2025/10/09 |
|
|
|
|