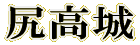 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
群馬県吾妻郡高山村尻高 |
| 築城者 |
長尾重国 |
| 築城年 |
応永8年(1401) |
| 廃城年 |
天正18年(1590) |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
高山村指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
尻高城は応永8年(1401)に白井城主の長尾重国が築き、三男の尻高左馬頭重儀が城主を務めた。武田信玄が上州侵攻を開始すると吾妻郡は信玄の家臣真田幸隆が攻略を受け持ち、元亀2年(1571)に尻高城は真田勢に降伏した。
天正2年(1574)に尻高景家は上杉謙信に帰服し、再び真田幸隆の攻撃を受け尻高城は落城した。信玄と謙信が没した後の尻高氏は北条氏に仕えており、尻高城も天正18年(1590)に北条氏の滅亡と同時に廃城となったと思われる。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 尻高城 |
|
南尾根 堀切 |
|
南尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 南尾根 曲輪 |
|
北尾根 登山道 |
|
北尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 尾根道 |
|
三の曲輪跡 |
|
本曲輪跡 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 堀切 |
|
二の郭 |
|
尻高城からの眺望 |
|
 |
尻高城は登り応えのある山城と聞かされていた。明確な堀切が2本で土塁は見られない簡素な山城だが、辺境の地にある山城というのは厳かな気持ちにさせてくれるので、一度は訪れてみたいと思っていた城だった。
居館が置かれた並木城を見たあと道標に従い登山道へと向かう。曲がり角を折れると石碑と案内板があるが、簡略な案内図があるのでそれを頭に叩き込んで細い山道を登っていった。この夏の台風は容赦なくこの山も襲ったようで倒木が多い。これは尻高城に限らずこの年の秋以降に登った山城に共通して言えることだった。
南へ伸びる尾根上にも遺構が残っている。鞍部を越えて少し登ると明確な堀切があった。それからしばらくは細い尾根上に並ぶ郭を見ながら進んでいくが、眼前に立ちはだかるのは急傾斜だった。親切なことにロープが張られているのでそれに頼りながら登る。急斜面が長く続くためにロープに掴まりながら登る時間が長くなるので手袋が必須となる。
砂礫と落ち葉に足を取られつつ登り終えると石宮があり、ここが主郭かと思ったがもう少し先だった。主郭もそれほど広さはなく、風除けの土塁もないので有事のときにしか利用されていなかったのだろう。主郭と二の郭を隔てる堀切は見事なものだった。二の郭にはぽつんぽつんと石宮が並んでいるが、何となく荘厳な風景だった。
尾根の南側はそうでもないが、北側は断崖絶壁で滑落したら命を失うことだろう。おっかなびっくりで覗いてみたが、あまり近づかないほうが良いと思う。事前の情報通り古さを感じさせる山城だったが、切り立つような峻険な地形に守られていたことで、これ以上の普請は必要としなかったのだろう。山頂で握り飯を2つ食べて昼食とした後は、枯葉に気を払いつつロープに身を委ねて下山した。 |
 |
 |
JR吾妻線「中之条」下車 たかやまバス「中山本宿」行で「戸室」下車 徒歩1時間20分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社 |
|
|
 |
2018/12/10 |
|
|
|
|