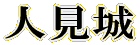 |
 |
| 別 名 |
堀籠屋敷 |
| 所在地 |
群馬県安中市松井田町人見 |
| 築城者 |
人見光行 |
| 築城年 |
鎌倉時代 |
| 廃城年 |
− |
| 現 状 |
山林・宅地 |
| 遺 構 |
郭・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
| |
 |
| |
 |
人見城は鎌倉時代に人見四郎光行が築いたとされる。人見氏は猪俣党の出身で現在の埼玉県と群馬県を地盤とし、どちらにもその居城と伝えられる城がある。東京都府中市にも人見屋敷という城館跡があるが、猪俣党人見氏との関係はわからない。
光行は元弘3年(1333)に北条高時の命を受け、楠木正成が籠る赤坂城を攻めたときに討死したを遂げた。このとき光行は73歳という当時としてはかなりの老齢だったと伝わる。ここまでが人見城にまつわる伝承だが、人見氏の居城だったことは肯定できても、その後に改修の手が入っているのはあきらかで、その勢力がはたして誰であったのかは特定されていない。永禄年間(1558〜70)に武田氏が西上州へ侵攻し、安中氏の城は大半が接収されたが、人見城の縄張りを見る限り、安中城との類似点が見受けられるので、現在見られる人見城の遺構は安中氏の手によるものと考えたい。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 人見城 |
|
鶯井戸 |
|
堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 馬出 |
|
馬出 土塁 |
|
三の郭 空堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 三の郭 空堀 |
|
三の郭 土塁 |
|
二の郭 土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 二の郭 空堀 |
|
二の郭 竪堀 |
|
主郭 空堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 空堀 |
|
四の郭 土塁 |
|
四の郭 空堀 |
|
 |
新幹線開通後の信越本線はすっかり寂れてしまい、国鉄の全盛時代を知る者にとっては寂しい限りである。軽井沢や上田までは上野から直通の普通列車が出ていて、それほど時間をかけず安く行けたが、横川駅で分断されてからは本当に不便になった。昭和の頃は温泉郷として賑わった磯部駅の駅前も、今では時代に取り残されたように閑散としている。逆に人がいないのは自分にとってはありがたく、城廻りの帰りに磯部温泉をしばしば利用した。
磯部駅からのんびり30分も歩くと人見城へ着いた。大宮神社境内の奥に人見城への入口があるが、足を踏み入れるとすぐに大きな堀切が現れた。その反対側には鴬井戸と呼ばれる水の手が今も水を湛えていた。南側は宅地化されているが、全体的に空堀がよく残されていた。来訪者にもわかりやすい縄張図と案内板が設置されているのも好感が持てる。人見城の空堀と土塁は写真で紹介すると迫力が伝わりにくいが、実際に現地で見るとかなり立派な遺構である。
最初の訪問から実に20年が過ぎて、本当に久しぶりの再訪となったが、見た瞬間にびっくりしたのは城跡の樹木が綺麗に刈り払われていたことだった。20年前は鬱蒼とした樹林と竹林に覆われていたが、唖然とするほどすっきりとして、まるで埼玉県の杉山城を見ているようだった。
地元の整備事業の賜物だろうが、おかげで以前とはまったく違う視点で散策を楽しめる。鶯井戸も難なく近づくことができ、そこからは堀底を歩きながら、人見城の全貌を存分に楽しむことができた。家屋が建つ場所は遠慮して歩いたが、堀底を歩くだけでも存分にその魅力を感じることができる。縦横無尽に巡らされた空堀を見ると否が応でも気分が高まる。
以前は藪のおかげで半分ぐらいしか魅力を感じ取ることができなかったが、今回は残されているほとんどすべての遺構を楽しんだ。古い歴史を誇る人見城だが、鎌倉時代の城というよりは完全なる戦国時代の城という印象を受ける。 |
 |
 |
JR信越本線「磯部」下車 徒歩30分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・人見城跡案内板 |
|
|
 |
2005/12/29・2025/02/20 |
|
|
|
|