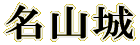 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
群馬県安中市郷原 |
| 築城者 |
安中重繁 |
| 築城年 |
永禄年間(1558〜70) |
| 廃城年 |
− |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・土塁・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
| 名山城は永禄年間(1558〜70)に安中重繁が築いたとされている。永禄5年(1561)に武田信玄が西上野への侵攻を開始したが、関東管領上杉氏に服属していた安中氏は、武田氏の侵攻に対して松井田城と安中城に兵を入れて備えたが、名山城はその中間に位置する繋ぎのための城として築かれたと思われる。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 名山城 |
|
搦手の曲輪 |
|
堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 切岸 |
|
堀切 |
|
堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 曲輪 |
|
曲輪 |
|
主郭 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 土塁 |
|
主郭 土塁 |
|
二の郭 |
|
 |
松井田駅で降りて中山道を東へ向かい、まだ登ったことがなかった名山城を目指した。以前は安中市の城によく見られる高札のような標識があったが、名山城の西側が太陽光パネルの敷地にされてしまったため、そのときに撤去されたようだった。
どこから取りつこうか迷ったが、中腹まで太陽光パネルが敷き詰められているので、フェンスに沿って登っていった。久しぶりに歩くのに難渋するような荊が混じった藪で、少しずつ慎重に進んでいく他はなかった。そうこうしているうちに搦手へ着いたようで、そこから進もうとするも鉄格子のような樹林に阻まれて撤退と前進を繰り返すことになった。
途中で根気が尽きて斜面を下り、再びフェンス沿いに歩いていると堀切が見えたので元気を取り戻して駆け上がった。堀切から曲輪へと上がり頭上を見上げると主郭の斜面が見えた。ここまで来ればあとは這い上がるだけである。幸いにして斜面は乾いており、樹木も多いので登りやすかった。
主郭は長方形でけっこうな広さがある。曲輪をしっかりと土塁が取り囲んでいる様子はなかなか壮観だった。土塁を越えると二の郭が拡がり、さらに複数の曲輪が斜面に連なる。そこから東へ延びる尾根にも曲輪が展開するが、そこまでは気力が続かなかった。
搦手が太陽光パネルで破壊されている以外は、全体的に遺構状態の良い山城だった。堀切の規模も大きかったし、主郭の土塁も立派なものである。もう少し藪がなければ良いのだが、こればかりは仕方がないし、破壊を免れただけでも良しとしなければなるまい。 |
 |
 |
JR信越本線「松井田」下車 徒歩50分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・群馬の古城/あかぎ出版・群馬県の中世城館跡/群馬県教育委員会 |
|
|
 |
2025/02/20 |
|
|
|
|