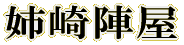 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
千葉県市原市姉崎 |
| 築城者 |
松平忠昌 |
| 築城年 |
慶長12年(1607) |
| 廃城年 |
寛永元年(1624) |
| 現 状 |
稲荷神社 |
| 遺 構 |
− |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
姉崎陣屋は江戸時代初期の慶長12年(1607)に設けられた陣屋で短期間で二度立藩している。奇しくも領主は結城秀康の息子たちで徳川家康と秀忠もそれなりの配慮をしたものと思われる。
最初は秀康の次男忠昌が1万石で姉崎藩主となった。元和元年(1615)に忠昌は下妻城へ移封され、元和5年(1619)に忠昌の弟直政が1万石で姉崎主となった。寛永元年(1624)に直政は越前大野で5万石を与えられたため姉崎陣屋は廃止された。 |
 |
この年の関東地方は経験したこともないような大寒波に見舞われた。例年なら山城に出かける時期だが、数十年ぶりと騒がれるほどの異常な寒さで、とても雪の残る山城へ登ろうという気力はなかった。少しでも寒さをしのげるように比較的温暖な千葉県を選択したが、この寒波を避けることはできなかったようで、朝7時の姉ヶ崎駅は手が凍えるほど冷え込んだ。滅多に手袋はしないのだが、さすがにこの日は手袋を装着した。
大通りから住宅地へと入ると陣屋らしい入り組んだ細い路地がある。しばらく歩くと稲荷神社があった。最初は公民館かと思ったが、鳥居と小さな社がある。陣屋跡を示すようなものは何もなかったが、大通りに戻ると立派な薬医門を持つ家があった。陣屋跡と重なる場所なので気になったが、人が暮らしている家なので撮影は控え、ポケットに手を突っ込みながら椎津城へと歩き出した。 |
 |
 |
JR内房線「姉ヶ崎」下車 徒歩10分 |
 |
|
 |
図説江戸三百藩 城と陣屋総覧/学研 |
|
|
 |
2018/02/06 |
|
|
|
|