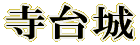 |
 |
| 別 名 |
台城 |
| 所在地 |
千葉県成田市寺台 |
| 築城者 |
馬場氏 |
| 築城年 |
室町時代 |
| 廃城年 |
天正18年(1590) |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・土塁・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
寺台城は千葉氏の一族に連なる馬場氏の居城とされる。築城年代は明らかではないが、室町時代に築かれた城と考えられる。その歴史は文献史料によって諸説あるため、一概にどれが正しいかは判断できないが、馬場氏代々の居城として存在してきたとされる。
永禄7年(1564)の国府台の戦いで里見義弘が、北条氏康に敗れて前線を後退させると、北条氏と同盟していた本佐倉城の千葉邦胤は勢いに乗じて上総へ兵を入れた。このときに千葉勢は利根川を渡河して佐竹氏領への侵攻を企てたが、この動きに応じた国人衆の中に寺台城主海保甲斐守の名が見られる。
天正18年(1590)の小田原の役で千葉氏は北条氏と運命を共にしたため、寺台城も寄せ手に攻められて落城し廃城となったが、この時に寺台城を守ったのは馬場伊勢守勝政もしくは海保甲斐守三吉と伝えられている。海保氏の遠祖里見氏は嘉吉元年(1441)の結城合戦で敗れ、上総海保荘へ逃れて千葉氏に仕えたとされるが、馬場氏は殿台城主で海保氏はその家臣として寺台城を与えられていたのかもしれないし、逆に海保氏が寺台城主で馬場氏が城代を務めていたとする解釈もあるらしい。海保三吉は戦後に徳川家康に仕えて寺台城を安堵されたが、徳川家康の命を受けた小野忠明によって自刃させられたとも伝わり、その最期は判然としていない。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 寺台城 |
|
四の郭 標柱 |
|
四の郭 海保甲斐守三吉の碑 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 堀切 |
|
三の郭 |
|
腰曲輪 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 二の郭 |
|
二の郭 |
|
二の郭 土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 腰曲輪 |
|
堀切 |
|
主郭 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 土塁 |
|
主郭 土塁 |
|
寺台城からの眺望 |
|
 |
房総は関東地方の中でも比較的温暖な地方だが、それは南総の館山市などのことであり、内陸はかなり冷え込む。京成成田駅で降り立ったときも手がかじかむほど気温が低かった。ここから寺台城までは歩いて30分ほどである。
成田山新勝寺の東参道に沿って歩いていると、台地へ続く道が見えたので登ってみた。そこには二の郭と三の郭を隔てる堀切があり、道は二の郭に当たる鷲神社へと続いていた。この曲輪は藪も少なくて見やすい状態であり、切岸を下ると寺台城の中でも最大の堀切へ至った。倒木が多いが歩けないほどではないので、堀底を縦横に歩いて規模を確かめた。そこから西側の腰曲輪へ登ったが、こちらも綺麗に平坦が出されて見やすかった。主郭は取りつく島もないような竹林である。頑張って北端にある四の郭まで進もうとしたが、とても歩ける状態ではなく一度台地から下ることにした。
再び東参道へと戻って歩いていくと寺台城への道標があった。再び台地へ上がると小さな堀切というか切通しがあり、先端に四の郭が展開していた。ここに城址標柱と最後の城主とされる海保甲斐守三吉の碑が建てられている。小高い丘だが眺望はとても良い。中心部が竹林と藪のために全貌を掴むのが難しい城だが、成田市内でも有数の規模を誇る城だけに散策は楽しかった。 |
 |
 |
JR成田線「成田」下車 JRバス「航空科学博物館」行で「寺台」下車 徒歩10分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・房総の古城址めぐり/有峰書店 |
|
|
 |
2025/01/18 |
|
|
|
|