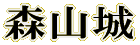 |
 |
| 別 名 |
飯田城・橘城・柑子城 |
| 所在地 |
千葉県香取市下飯田 |
| 築城者 |
東胤頼 |
| 築城年 |
建保6年(1218) |
| 廃城年 |
天正18年(1590) |
| 現 状 |
山林・農地 |
| 遺 構 |
郭・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
| |
 |
| |
 |
森山城は建保6年(1218)に千葉常胤の六男東六郎胤頼が須賀山城に代わる居城として築いた城である。2つの城は同じ台地続きにあるので、須賀山城は森山城の出城のような存在となったのだろう。
築城から東氏の居城として胤頼、重胤、胤行の三代が在城したが、承久3年(1221)に胤行は美濃山田荘の地頭として赴任したため、森山城は東氏の城代が置かれたという。康正元年(1455)に千葉氏は一族の馬加康胤と原胤房が当主の千葉胤宣との間で内紛が勃発し、多古城へ追いやられた胤宣は自刃した。この窮地を救うために東常縁が美濃から出陣し、森山城に入城して周辺の豪族たちを糾合して馬加城を攻めるなど関東で奮戦した。
戦国時代の森山城は海上氏を継いでいた千葉胤富が城主となるが、弘治3年(1557)に胤富は千葉氏の当主の座を奪い本佐倉城へ入ったため、森山城は粟飯原氏、原氏が城主を歴任した。北条氏が版図を拡大すると千葉氏も従属を強いられ、天正18年(1590)の小田原の役で北条氏とともに千葉氏も没落し、ここに森山城はその歴史を閉じることとなった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 森山城 |
|
鳳凰曲輪 東常縁墳墓 |
|
鳳凰曲輪 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 大手虎口 |
|
三城 |
|
空堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 仲城 土塁 |
|
仲城 |
|
仲々城 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 仲々城 |
|
土橋 |
|
奥仲城 土橋と虎口 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 空堀 |
|
奥仲城 土塁と標柱 |
|
奥仲城 |
|
 |
須賀山城の壮大な遺構を堪能したあとは台地続きにある森山城を訪ねた。心細くなるような細い道をたどると東常縁の墳墓とされる円墳が残っているが、ここは森山城の鳳凰曲輪にあたる。
いかにも房総の城らしい広大な面積を誇る城だが、反面で台地上は農地や牧場として利用されているため、須賀山城のような緊張感は感じられず、とても牧歌的な雰囲気の中での散策となった。まだ9月なので堀底は雑草と雑木に覆われており、撮影しても現地で見るほどの迫力が伝えられないが、実に壮大な遺構が現地には残されている。
同じ千葉県にある横芝光町の坂田城と似た巨大戦艦の甲板を歩いているような錯覚を覚えるような城で、実質的な主郭に相当する仲々城と呼ばれる曲輪には牛舎が並び、牛たちがのんびりと暮らしていた。人が珍しいのだろうか、通り過ぎる自分に牛たちが視線を浴びせる。城跡を歩いていると牛舎や豚舎、それに養鶏場に出会うことが多いが、森山城の牛舎は管理が行き届いているのか、強烈な臭気はまったく感じられずほのぼのとしていた。
屈曲した道を歩いていくと馬出しと緩やかな曲線を描く土橋があり、広い空堀を経て奥仲城と呼ばれる根古屋地区に至る。ここに倒れかけた標柱と案内板が設置されていたが、あまりにも面積が広すぎてここまで来ると疲れを感じた。このあたりで蒸し暑さに参ってしまい、少し足早に鳳凰曲輪へと引き返し、次なる目的地を模索することにした。 |
 |
 |
JR成田線「笹川」下車 徒歩45分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・房総の古城址めぐり/有峰書店・森山城跡案内板 |
|
|
 |
2025/09/11 |
|
|
|
|