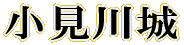 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
千葉県香取市小見川 |
| 築城者 |
粟飯原朝秀 |
| 築城年 |
建久10年(1199) |
| 廃城年 |
元和5年(1619) |
| 現 状 |
小見川城山公園 |
| 遺 構 |
郭・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
小見川城は建久10年(1199)に千葉氏の一族である粟飯原朝秀によって築かれたとされ、それからは粟飯原氏代々の居城となった。粟飯原氏の祖先は千葉常基であるが、別流の平良兼を祖先とする粟飯原氏も存在し、朝秀は良兼流粟飯原氏の後裔という。常基の子有胤は男子に恵まれなかったため、伊勢寿丸と名乗っていた朝秀を養子に迎え、伊勢寿丸は源頼朝から一字を賜り朝秀と名乗るようになった。
その後も粟飯原氏の居城として最後の城主となった俊胤まで続いたが、天文年間(1532〜55)には里見氏の家臣正木氏の侵攻を受け、粟飯原左衛門は降伏したという。天正18年(1590)の小田原の役で粟飯原俊胤は北条氏に動員され小田原城の守備についたが、このときに小見川城も豊臣軍に攻められて落城した。俊胤は徳川家康の五男信吉に仕えたが、信吉の没後は浪人して姓を鏑木と改めた。
粟飯原氏が去った後の小見川城はしばらくの空白期間を経て、文禄3年(1594)に家康の家臣松平家忠が入ったが、家忠は慶長5年(1600)に関ヶ原の戦いの前哨戦となった伏見城の戦いで討死し、子の忠利は翌年に三河深溝へ移封され、土井利勝、安藤重信が城主を歴任した後に廃城となった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 小見川城 |
|
三の郭 |
|
腰曲輪と石塔 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 赤橋と堀切 |
|
堀切 |
|
腰曲輪 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 二の郭 虎口 |
|
二の郭 |
|
主郭 虎口と空堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 空堀 |
|
空堀 |
|
主郭 虎口 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 土橋 |
|
主郭 土塁 |
|
主郭 土塁 |
|
 |
軽い熱中症気味で向かった小見川城だったが、道中で飲み干したアクエリアスのおかげで回復し、城山公園に着いてからは元気そのもので歩き回った。小見川城は公園化のためにあまり遺構を残していないというのが事前の知識とあったが、実際に訪れてみるとまったくそんなことはなく、土塁や空堀と土橋、曲輪を仕切る堀切がよく残っていて大満足だった。
公園化されているおかげで駐車場も完備されて綺麗なトイレもあり、散策路も整備されている。清風荘の建つあたりが三の郭で堀切に架かる赤橋を渡ると遊具が置かれた腰曲輪がある。城址には古墳が点在していて、小見川城が築かれる前から人々の営みが送られていたことがわかる。
二の郭は忠霊塔の建つ公園として整備されているが、改変を受けているものの虎口が残り、曲輪も櫓台のような土盛りがあり、城跡らしい雰囲気は存分に感じることができた。深い空堀には土橋が架かり、土塁で守られた主郭の虎口は厳重そのものだった。主郭の大半が浄水場の建設で削り取られているのは残念で、これだけが小見川城の割引材料となってしまうのだが、それを除けば十分に訪れる価値のある城だった。 |
 |
 |
JR成田線「小見川」下車 徒歩30分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・房総の古城址めぐり/有峰書店・小見川城跡案内板 |
|
|
 |
2025/09/11 |
|
|
|
|