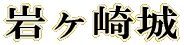 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
千葉県香取市佐原 |
| 築城者 |
国分氏 |
| 築城年 |
戦国時代 |
| 廃城年 |
慶長7年(1602) |
| 現 状 |
山林・稲荷神社 |
| 遺 構 |
郭・土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
岩ヶ崎城は千葉氏の一族である国分氏が戦国時代に大崎城に代わる居城として築いたとされる。天正18年(1590)に小田氏治と栗林義長に攻められて落城したというが、これは『東國戦記実録』に記されているのみで信憑性は低く、氏治はお家再興に執念を燃やして常陸の佐竹氏と争い北条氏と連携していたため、香取郡へ攻め込む理由がない。
実際には周辺の諸城と同様に小田原の役で没落の憂き目を見たというのが真相だろうが、北条氏に代わり関東一円を与えられた徳川家康は幼少期からの家臣である鳥居彦右衛門元忠を下総矢作の領主とした。元忠は矢作の大崎城に入ったが、利根川沿いの台地先端に築かれていた岩ヶ崎城を新たな居城とすることに決めた。元忠は改修を急がせるため領民に過酷な労働を強いたようだが、慶長5年(1600)に伏見城の城将に任命され、関ヶ原の戦いの前哨戦で西軍の大軍を迎えて討死した。子の忠政は磐城平城で10万石を与えられたため岩ヶ崎城は廃城となった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 岩ヶ崎城 |
|
虎口 |
|
土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 曲輪 |
|
土塁 |
|
土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 土塁 |
|
虎口 |
|
曲輪と土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 稲荷神社 |
|
土塁 |
|
主郭 |
|
 |
岩ヶ崎城へたどり着いたのは既に夕闇が迫る時間帯だった。日没までにはまだ余裕があるはずだったが、曇天模様だったためにいつもより暗くなるのが早かったため、岩ヶ崎城は少し足早で駆け抜けるしかなかった。
城址は鎮守の森として鬱蒼としている。デジタルカメラの性能のおかげもあって鮮明な画像となっているが、実際にはこれよりももっと暗い。台地の西半分は宅地化されて遺構は壊滅しているが、東半分は稲荷神社や愛宕神社の境内となっているおかげで、思っていた以上に遺構はよく残されている。暗かったために曲輪の配置がよくわからない上、見落とした遺構も多いと思うが、巨大な土塁は見る者を圧倒する迫力があった。主郭は稲荷神社背後の急峻な地形となっていて登ることはしなかったが、そそり立つような城壁は見事である。
香取市に始まり東庄町まで進出し、最後はまた香取市へと戻り、この日の旅は終わりを告げた。まだまだ見ておきたい城が多い場所であることは確かだが、千葉県は開発優先の風潮が昔から強く、最近はともすれば日本の文化や自然を破壊するようになった。近い将来に今は健在な城跡も大半が消滅してしまう恐れがあるので、できる限り探訪を続けていきたいと思うし、この美しい国を守らなければならないという使命感を強く感じるのである。 |
 |
 |
JR成田線「佐原」下車 徒歩20分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・房総の古城址めぐり/有峰書店 |
|
|
 |
2025/09/11 |
|
|
|
|