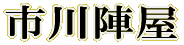 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門 |
| 築城者 |
江戸幕府 |
| 築城年 |
明和2年(1765) |
| 廃城年 |
明治2年(1869) |
| 現 状 |
宅地 |
| 遺 構 |
− |
| 移築建造物 |
門 |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
市川三郷町指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
| 市川陣屋は明和2年(1765)に駿河紺屋町陣屋の出張陣屋として設置された陣屋で、代官小田切新五郎が3万石余りの支配地を管理した。寛政7年(1795)に建て替えられ本陣屋へと昇格し、安政の大地震で難民救済に奔走した荒井清兵衛、馬鈴薯の普及に尽力した中井清大夫ら名代官を輩出した。天保6年(1835)の火事で官舎一棟を除いて全焼し、明治2年(1869)に廃止された。 |
 |
|
|
 |
身延線に乗るのは9年ぶりのことだった。ICカード未対応の駅が多く、いつも乗り越し精算を迫られるが、今回も同様だった。切符を買った国分寺駅の券売機では酒折駅までの乗車券しか買えず、早朝ではみどりの窓口も開いていない。窓口での対面販売が失われて久しいが、人件費削減にばかり注力しすぎて肝心のサービスは低下している。
市川本町駅で下車するときに運転士に精算を依頼すると、車載電話でセンターとやり取りして酒折駅からの差額を計算してくれたが、すいぶんと時間がかかり逆に申し訳ない気持ちになった。長旅だったので駅前のベンチに腰かけて、吸い殻入れの前で煙草を一服していると、いつものようにスズメバチが猛然と襲い掛かってきたので、そそくさと煙草を消して立ち去った。彼らはなぜいつもあんなに怒っているのだろう。
駅から市川陣屋までは目と鼻の先といった距離である。跡地に石碑が建ち陣屋で使われた移築門が保存されている。現存門があるというだけで満足感が各段に異なるが、木造の門だけに保存も大変だろうし、維持費もかかるだろうと思う。日本政府はもう少し日本人と日本の街や文化の維持に金をかけるべきだと思う。 |
 |
 |
JR身延線「市川本町」下車 徒歩5分 |
 |
|
 |
甲斐の山城と館/戎光祥出版 |
|
|
 |
2025/09/28 |
|
|
|
|