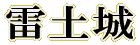 |
 |
| 別 名 |
板木城 |
| 所在地 |
新潟県魚沼市板木 |
| 築城者 |
上田長尾氏 |
| 築城年 |
天文年間(1504〜20) |
| 廃城年 |
慶長3年(1598) |
| 現 状 |
山林 |
| 遺 構 |
郭・土塁・堀切 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
魚沼市指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
魚沼市と南魚沼市の境界に位置する標高357mの山城で、戦国時代の天文年間(1504〜20)に上田長尾氏が築いたという。魚沼市では板木城の名で呼ばれ南魚沼市では雷土城と呼ばれている。根古屋は坂木集落にあり魚沼市の文化財に指定されているので、本来は板木城として紹介すべきだが、雷土城のほうが何となく山城らしいので矛盾は承知の上で雷土城として紹介する。
鋭角な堀切が緊張感を感じさせる遺構は、天正6年(1578)に起きた御館の乱で北条氏が越後へ侵攻したときに上杉景勝が改修したと考えられている。廃城時期は明らかでないが、慶長3年(1598)に景勝が会津へ移封となったときと考えて良いと思う。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 雷土城 |
|
登山道 |
|
西尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 西尾根 堀切 |
|
西尾根 堀切 |
|
西尾根 堀切 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 西尾根 堀切 |
|
主郭 虎口 |
|
主郭 虎口 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 |
|
主郭 |
|
城址碑 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 東尾根の堀切 |
|
東尾根の堀切 |
|
雷土城からの眺望 |
|
 |
友人たちとの新潟遠征で登ったのが雷土城と尾根続きにある湯谷城だった。西尾根の電波塔が建つ場所に車を停めて登山道へと入り、城跡へ到達するまでに標高322mのピークをひとつ越えるのだが、このピークが往復ともに厄介だった。
ピークから10分ほど歩くと最初の堀切があり城域に入る。厳重な二重堀切は垂直にそそり立ち、鎖に掴まりながら注意深く登った。段郭を経て中心部へと道は続く。北側斜面には越後の城でよく見られる連続竪堀があるらしいが、斜面にはびっしりと木が生え揃いまったくわからなかった。登山道は尾根の端を登って主郭へ着くようになっているが、往時は馬出を通り折れ曲がるようにして主郭の枡形虎口へ続いているように見える。
主郭から二の郭へかけても笹薮が生い茂りとても入れなかったが、藪の中に土塁と本来の虎口があるようだった。北と南の尾根にも厳重すぎるほどの郭を配置しているが、やはり樹木が繁茂しているために下りられるような状態ではない。東尾根にも鋭角な堀切が連続して守りを固めており、小さな郭を経て尾根道は支城である湯谷城へと続いていく。
以上が雷土城の全容だが、想像していたよりも荒々しく迫力を感じることができる山城だった。こういった工夫のされ方を見ると戦国時代の終焉近くまで使用されていた雰囲気が強く感じられる。 |
 |
 |
JR新幹線・上越線「浦佐」下車 徒歩2時間 |
 |
|
 |
藪神衆の苦悩と誇り:魚沼の戦国事情/新潟日報事業社・上杉謙信ゆかりの地を訪ねて/新潟日報事業社 |
|
|
 |
2018/11/11 |
|
|
|
|