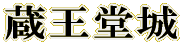 |
 |
| 別 名 |
蔵王城 |
| 所在地 |
新潟県長岡市西蔵王 |
| 築城者 |
中条氏 |
| 築城年 |
南北朝時代 |
| 廃城年 |
元和2年(1616) |
| 現 状 |
蔵王公園・金峯神社 |
| 遺 構 |
郭・石積・土塁・水堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
長岡市指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
蔵王堂城は南北朝時代に越後で北朝方に属していた中条氏が築いた城で、蔵王権現が祀られた蔵王堂があることからその名がついた。南北朝時代の越後は新田氏の勢力が及んでいたため、正平7年(1352)には南朝の軍勢から攻撃を受けた。
室町時代になると越後守護代長尾氏の分家となる古志長尾氏の居城となり、長尾景晴が城主となり孝景が栖吉城を居城とするまで、古志長尾氏四代が蔵王堂城に拠った。やがて上杉謙信の叔父にあたる長尾為重が蔵王堂城を修築し、慶長3年(1598)に上杉景勝が会津へ移封されるまで上杉氏の家臣松川大隅守修衡が城主となった。
景勝に代わって越後の国主となった堀秀治が春日山城主となると、弟の堀親良が蔵王堂城主となるが、堀氏が断絶すると松平忠輝の家臣山田勝重が城主となった。元和2年(1616)に忠輝は改易され、かつて蔵王堂城主だった堀直寄が返り咲いたが、直寄は水害に悩まされてきた蔵王堂城に代わる居城として長岡城を築いたため、蔵王堂城は廃城となった。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 蔵王堂城と堀直寄像 |
|
金峯神社 |
|
水堀 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 水堀 |
|
水堀 |
|
主郭 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 毘沙門堂 |
|
標柱 |
|
城址碑 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 土塁 |
|
主郭 土塁 |
|
堀直寄像 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 主郭 土塁 |
|
主郭 土塁 |
|
石積 |
|
 |
長岡への旅の目的は蔵王堂城を訪ねることだった。長岡城は遺構が皆無のため10分もあれば見尽くしてしまう。蔵王堂城も大部分が失われてしまい、残るのは主郭のごく一部だが、モノクロで紹介されていた水堀と土塁の美しさに魅せられていたのが理由である。
好天に恵まれたおかげで蔵王堂城の美しさを存分に堪能することができたが、特に土塁は間近で見るとその規模に驚かされる。水堀に沿って残る土塁は小山のように大きく、毘沙門堂などが建ち並ぶ背後に残る土塁もまた見事なものだった。土塁の上にはわずかながら石積が見られるが、これが当時の遺構なのかはわからない。
しばらく土塁に上がったり水堀の端を散策するなどしていたが、いつまでも見ていたい衝動に駆られるような城である。蝉時雨の中をゆっくりとした時間を過ごしていたが、あまり長く時間を取るわけにもいかず、後ろ髪を引かれる思いで蔵王堂城を後にした。 |
 |
 |
JR上越新幹線・信越本線「長岡」下車 越後交通バス「上見附車庫前」行で「新町2丁目」下車 徒歩15分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社 |
|
|
 |
2025/09/19 |
|
|
|
|