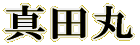 |
 |
| 別 名 |
真田幸村出丸 |
| 所在地 |
大阪府大阪市天王寺区餌差町 |
| 築城者 |
真田信繁 |
| 築城年 |
慶長19年(1614) |
| 廃城年 |
慶長20年(1614) |
| 現 状 |
明星高等学校・真田山小学校 |
| 遺 構 |
− |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
豊臣秀頼の招きに応じて紀州九度山を脱出し大坂城へ入城した真田信繁は、慶長19年(1614)に大坂城の南側の台地に砦を築いた。真田丸の範囲はこれまで真田丸公園と三光神社から西に広がる台地と考えられてきたが、大河ドラマの放送で人気に拍車がかかり、新たな考証に基づき明星高校のある高台がその跡地と推定された。
信繁は真田丸で徳川軍を駆け悩ませ、大坂冬の陣では天下の大軍を相手に互角に渡り合った。講和が結ばれたあと徳川家康は大坂城の堀を埋め立て、さすがの名城も裸城となってしまい、大坂夏の陣では籠城もままならず、統率も取れない状況下での野戦となった。堅固な真田丸もその防御力を削がれたため、信繁は毛利勝永らと家康の本陣を急襲し、松平忠直の軍勢を蹴散らし家康に肉薄したが、最後は力尽き西尾甚左衛門宗次に首を授けたという。 |
 |
|
|
 |
京都を振り出しに奈良から和歌山へ移動した壮大な近畿旅行は終わりを迎えつつあった。移動距離は長かったが近畿は鉄道網が関東よりも充実していて意外と楽に移動ができた。関東だと都心近郊以外はほとんどがローカル線で列車の本数は極端に少なくなり、第3セクターの路線が多いために運賃も割高となる。おまけにバスが少ないために今回の旅のような縦横無尽の移動はまず不可能と言っていい。
旅の終わりは大坂城と決めていたので新今宮駅で南海電車からJRに乗り換えたが、途中の玉造に到着したときに行くか行くまいか迷っていた真田丸を訪ねる決断が瞬時についた。列車の発車ベルが鳴り終える直前に脱兎の如く席を立ち扉をすり抜けたが、ここで行かなければ必ず後悔すると思い体が勝手に動いていた。
紀州の九度山から抜け出した信繁は豊臣秀頼に迎えられて一手の将となったが、浪人衆の扱いは低く統制も取れていなかったのは確かである。だが大坂冬の陣での彼らの奮闘ぶりは今も人の心を熱くさせるし、まったく勝ち目のなくなった夏の陣でも徳川家康を危機一髪のところまで追いつめた。歴史上の人物の中でも真田氏の歴代当主は魅力的で好きな武将が多く、信州上田や上州沼田などの真田氏関係の史跡はほとんど廻っている。そんな中でも信繁が壮烈な死闘を演じた真田丸だけはぜひとも訪ねておきたかった。
三光神社に采配を振るう信繁の像が建ち、真田の抜け穴と伝わる岩穴が残るが、史実はどうあれロマンを掻き立てる。明星高校の敷地に真田丸の顕彰碑が建てられ、その向かいの心洞寺にも真田幸村出丸城跡の石碑があるが、周辺の地形から考えて最近の考察にそれほどの狂いはないと思う。はっきりとわかる段差があちこちで見られ、大坂城方面へ歩くと総構の空堀にあたる広く落ち込んだ地形が残っている。それを自分の足で歩いてみて実感し、豊臣期大坂城の巨大さに驚く思いがした。 |
 |
 |
JR大阪環状線「玉造」下車 徒歩15分 |
 |
|
 |
別冊歴史読本 真田一族/新人物往来社 |
|
|
 |
2019/10/09 |
|
|
|
|