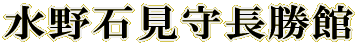 |
 |
| 別 名 |
赤浜陣屋 |
| 所在地 |
埼玉県大里郡寄居町赤浜 |
| 築城者 |
水野長勝 |
| 築城年 |
天正10年(1582) |
| 廃城年 |
正保4年(1647) |
| 現 状 |
昌国寺 |
| 遺 構 |
土塁・空堀 |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
− |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
水野石見守長勝は尾張緒川城主の水野成清の子として生まれたが、2歳のときに父を失い母の再婚先の松平家広に養育された。成長した長勝は織田信長に仕えたが、天正10年(1582)に本能寺の変で信長が横死すると北条氏政に仕えた。
天正18年(1590)に北条氏が滅ぶと、遠縁になる徳川家康に召し出されて武蔵男衾郡のうちで8百石を与えられた。このときに赤浜に陣屋を構えたというが、北条氏が健在だった時代には鉢形城で一郭を任されているので、当時から赤浜に館を構えていたと思う。
慶長7年(1602)に伏見城番となり石見守に叙任しし、子の忠貞は5千石を知行し正保4年(1647)に大和へ領地替えとなるに及んで赤浜陣屋は廃された。 |
 |
 |
|
 |
|
 |
| 昌国寺 |
|
空堀 |
|
土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 土塁と空堀 |
|
土塁と空堀 |
|
土塁 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 土塁 |
|
土塁 |
|
水野家墓所 |
|
 |
ずいぶんと前に昌国寺を訪れたとき、見事な土塁が残っていたのを見てとても驚いた記憶がある。そのときは5月でかなり草木が成長していたが、土塁の規模はよくわかった。12年後に再訪したときは草木も伐採されて土塁の美しさが強調されていた。
昌国寺はやや寂しげな寺で本堂も小さい。水野家の墓という案内表示はあるが、居館跡ということには触れられていなかった。境内を囲むようにして土塁と空堀が残るが、南面はやや風化している。北側の土塁は見事なもので戦国時代の居館という風情が感じられる。以前は何気なく見ただけの水野家墓所だが、周囲を土塁で囲まれて独立した曲輪のようだった。
周辺の風景ものどかで気持ち良い。近くに川の博物館があったが、城館探訪を優先したために立ち寄らなかった。とても興味があるのでそのうち訪ねてみたい。 |
 |
 |
東武東上線「男衾」下車 徒歩45分 |
 |
|
 |
日本城郭大系/新人物往来社・小川町の歴史 通史編上巻/小川町 |
|
|
 |
2005/05/06・2017/02/01 |
|
|
|
|