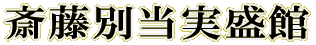 |
 |
| 別 名 |
− |
| 所在地 |
埼玉県熊谷市西野 |
| 築城者 |
斎藤実盛 |
| 築城年 |
平安時代末期 |
| 廃城年 |
− |
| 現 状 |
宅地 |
| 遺 構 |
− |
| 移築建造物 |
− |
| 再建建造物 |
− |
| 史跡指定 |
熊谷市指定史跡 |
| 評 価 |
 |
|
|
 |
斎藤実盛は藤原利仁の後裔で越前で生まれ斎藤実直の養子となり、武蔵幡羅郡長井庄を本拠としたため長井別当と通称された。実盛は源氏の棟梁である源義朝に仕えていたが、義朝の弟義賢が武蔵大蔵館を拠点として上州までを勢力範囲としていたため、自身の本拠地から近い義賢に仕えるようになった。
久寿2年(1155)に義朝の長男義平が大蔵館を急襲し、義賢を討ち取る事態が起きた。義賢の子駒王丸はまだ幼児だったが、これを匿い信濃への逃亡を助けたのが実盛であり、駒王丸は後の木曾義仲である。
平治の乱で義朝が敗れて源氏が衰退すると実盛は平氏に仕えたが、治承4年(1180)に義仲が挙兵し、寿永2年(1183)の加賀篠原の戦いで実盛は手塚光盛に討ち取られた。このとき実盛は老齢であったが、白髪を黒く染めて出陣したという。
義仲が首実検をしているとき、討ち取った兜首の中から実盛の首を探したが見つけることができず、妙齢の武士の首を池で洗うと毛染めが落ちて白髪の実盛とわかり、義仲はその首に取りすがって泣いたという。最後の戦いに臨む実盛の気持ちがひしひしと伝わる逸話である。 |
 |
|
|
 |
夏の盛りに友人と熊谷市の城館を訪ねた。この日は旧妻沼町の城と館が中心だったので、当然のように長井ノ別当実盛に関わる史跡が中心となった。実盛の悲劇的な最期はとても有り得ないような運命の巡り合わせを感じさせてくれる。
肝心の居館跡は何も残っていなかった。福川沿いの土手を歩くと実盛塚と呼ばれる場所があり、館跡の石碑と案内板が建つ。古くからここが斎藤実盛の居館跡と伝えられてきた場所で、戦前までは埼玉県の史跡に指定されていたが、今ではそれも解除され伝承地に格下げされた。 |
 |
 |
JR北陸新幹線・高崎線「熊谷」下車 朝日バス「妻沼」行で「井殿橋」下車 徒歩10分 |
 |
|
 |
実盛公遺跡探訪遊歩道/熊谷市教育委員会・武蔵武士/まつやま書房 |
|
|
 |
2012/07/31 |
|
|
|
|